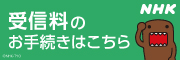マイコンテンツや、お客様情報・注文履歴を確認できます。

閉じる
カートに追加されました
つまずきやすい日本語

商品紹介
言葉の本質をつかめば、コミュニケーションが楽しくなる!
誰もが経験する「会話の行き違い」。なぜそうなるのか? 日本でいちばん言葉を偏愛し、観察を続ける辞書編纂者が、豊富な実例をもとに原因と対処法を考える。歴史や語源など、言葉の根っこを学びながら「言葉との付き合い方」を身に付ける、知的で実践的な日本語入門!
―「はじめに」より―
私は、国語辞典を作る仕事を通じて、日々、ことばと格闘しています。世の中のいろいろなことばを観察したり、ことばについて考えたりするのが大好きです。
今回の講座は、「つまずきやすい日本語」と題しました。「つまずく」とはやや分かりにくい表現かもしれませんが、「失敗する」、とりわけ「誤解を生む」ということだと考えてください。
人は何歳になっても、ことばでつまずきます。ことばが元で、とんでもない勘違いをしたり、人とすれ違ったり、人を傷つけたり、傷つけられたりを繰り返しています。ことばというものは、本当に迷惑なトラブルメーカーです。
(中略)私たちに必要なことは、2つあります。ひとつは、ことばという、「つまずき」を誘いやすい道具の性質をよく知ることです。そして、もうひとつは、その道具をなるべく失敗しないように使う方法を考えることです。この講座では、主にこの2つのことを扱います。
目次
はじめに 「間違いやすい日本語」ではない
第1章 私たちのことばは同じでない
第2章 時間が理由で起こる「つまずき」
第3章 場所・場合が理由で起こる「つまずき」
第4章 「つまずき」を避ける方法
おわりに ことばを使いこなしたい
日本語につまずかないためのブックガイド
第1章 私たちのことばは同じでない
第2章 時間が理由で起こる「つまずき」
第3章 場所・場合が理由で起こる「つまずき」
第4章 「つまずき」を避ける方法
おわりに ことばを使いこなしたい
日本語につまずかないためのブックガイド
著者情報
飯間 浩明 著
1967年、香川県高松市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。同大学院博士課程単位取得。専門は日本語学。『三省堂国語辞典』編集委員。著書に『辞書を編む』(光文社新書)、『三省堂国語辞典のひみつ』(新潮文庫)、『国語辞典のゆくえ』(NHK出版)、『ことばハンター 国語辞典はこうつくる』(ポプラ社)、『伝わるシンプル 文章術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。2011~13年にNHK Eテレ「どうも!日本語講座です。」の講師を、2015~16年に「使える!伝わる にほんご」の総合監修を担当。2018年にNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演。
商品情報
- 発売日
- 2019年03月25日
- 価格
- 定価:737円(本体670円)
- 判型
- A5判
- ページ数
- 104ページ
- 雑誌コード
- 6407242
- Cコード
- C9481(日本語)
- ISBN
- 978-4-14-407242-0
関連商品

役に立つ古典

考える教室 大人のための哲学入門

みんなの密教

傷つきのこころ学

「書く」って、どんなこと?

哲学のはじまり

使える儒教

ここちよさの建築

感性でよむ西洋美術

教養としての俳句

ともに生きるための演劇

はじめての利他学

フェミニズムがひらいた道

キリスト教の核心をよむ

しあわせの哲学

くらしのための料理学

お経で読む仏教

自分ごとの政治学

落語はこころの処方箋

「読む」って、どんなこと?

本の世界をめぐる冒険

はみだしの人類学

人生が面白くなる 学びのわざ

からだとこころの健康学

ブッダが教える愉快な生き方

役に立つ古典

考える教室 大人のための哲学入門

みんなの密教

傷つきのこころ学

「書く」って、どんなこと?

哲学のはじまり

使える儒教

ここちよさの建築

感性でよむ西洋美術

教養としての俳句

ともに生きるための演劇

はじめての利他学

フェミニズムがひらいた道

キリスト教の核心をよむ

しあわせの哲学

くらしのための料理学

お経で読む仏教

自分ごとの政治学

落語はこころの処方箋

「読む」って、どんなこと?

本の世界をめぐる冒険

はみだしの人類学

人生が面白くなる 学びのわざ

からだとこころの健康学

ブッダが教える愉快な生き方

役に立つ古典

考える教室 大人のための哲学入門
Copyright NHK Publishing, Inc.