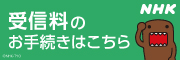マイコンテンツや、お客様情報・注文履歴を確認できます。

閉じる
カートに追加されました
果てしなき 石ノ森章太郎

商品紹介
天才を超えた萬画家・石ノ森章太郎の「とてつもなさ」を語り尽くす一冊!
2018年9月に放送され大反響を呼んだ「100分de名著」スペシャル「100分de石ノ森章太郎」が、満を持していよいよ別冊ムック化!石ノ森章太郎の魅力・才気・緻密さを余すことなく語る尽くした一冊。4人の論考に加え、カラー口絵、竹宮惠子・島本和彦氏へのインタビューも載録。
目次
はじめに―石ノ森章太郎の「残留思念」が私たちを形作った
第1章『さるとびエッちゃん』ヤマザキマリ
~「おかしなあの子」が示す柔らかな生き方
*「女の子」や「傍観者」を勇気づけた石ノ森の先駆性
竹宮惠子インタビュー『マンガ家入門』からすべてが始まった!
第2章『サイボーグ009』名越康文
~描かれた思春期の苦悩と困難
*ダイバーシティを先取りし、「思春期の少年」のココロを知り尽くした石ノ森の心智
島本和彦インタビュー「石ノ森先生が天才だと思う、ワタクシ的な理由」
第3章『佐武と市捕物控』夏目房之介
~青年漫画の革命児
*「マンガの文法」を開拓し時代と切り結んだ石ノ森の斬新さ
石ノ森章太郎略年譜
第4章『仮面ライダー』宇野常寛
~受け継がれる コンセプター・石ノ森の遺伝子
*コンセプターとしてキャラクターデザインに革命を起こした石ノ森のセンス
○ほか:カラー口絵8ページ/ショートコラム「27歳で上梓した『マンガ家入門』」
第1章『さるとびエッちゃん』ヤマザキマリ
~「おかしなあの子」が示す柔らかな生き方
*「女の子」や「傍観者」を勇気づけた石ノ森の先駆性
竹宮惠子インタビュー『マンガ家入門』からすべてが始まった!
第2章『サイボーグ009』名越康文
~描かれた思春期の苦悩と困難
*ダイバーシティを先取りし、「思春期の少年」のココロを知り尽くした石ノ森の心智
島本和彦インタビュー「石ノ森先生が天才だと思う、ワタクシ的な理由」
第3章『佐武と市捕物控』夏目房之介
~青年漫画の革命児
*「マンガの文法」を開拓し時代と切り結んだ石ノ森の斬新さ
石ノ森章太郎略年譜
第4章『仮面ライダー』宇野常寛
~受け継がれる コンセプター・石ノ森の遺伝子
*コンセプターとしてキャラクターデザインに革命を起こした石ノ森のセンス
○ほか:カラー口絵8ページ/ショートコラム「27歳で上梓した『マンガ家入門』」
著者情報
ヤマザキマリ 著
漫画家、エッセイスト、東京造形大学客員教授。1967年東京都生まれ。17歳のときに渡伊、国立フィレンツェ・アカデミア美術学院で油絵と美術史を専攻。エジプト、シリア、ポルトガル、アメリカと各地で活動したのち、現在はイタリアと日本に拠点を置く。1997年より漫画家として活動開始、2010年、『テルマエ・ロマエ』(エンターブレイン)で第3回マンガ大賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。ほかの主な漫画作品に『スティーブ・ジョブズ』(講談社)、『プリニウス』(とり・みきとの共作、新潮社)など。エッセイに、人生の自由さと楽しさを教えてくれた母親との日々を描いた『ヴィオラ母さん――私を育てた破天荒な母・リョウコ』(文藝春秋)のほか、『国境のない生き方――私をつくった本と旅』(小学館新書)、『たちどまって考える』(中公新書ラクレ)など多数。2015年度芸術選奨新人賞受賞、2019年、日本の漫画家として初めてイタリア共和国星勲章・コメンダトーレを受章。
名越 康文 著
精神科医。相愛大学、高野山大学客員教授。1960年、奈良県生まれ。専門は思春期精神医学、精神療法。近畿大学医学部卒業後、大阪府立中宮病院(現:大阪府立精神医療センター)にて、精神科救急病棟の設立、責任者を経て、1999年に同病院を退職。引き続き臨床に携わる一方で、コメンテーターとして映画評論、漫画分析などの様々な分野で活躍する。著書に『SoloTime「ひとりぼっち」こそが最強の生存戦略である』『驚く力――矛盾に満ちた世界を生き抜くための心の技法』(夜間飛行)、『〈新版〉自分を支える心の技法』(小学館)などがある。近年は自ら作曲作詞を手掛けるオリジナル・バンド「THE BARDIC BAND」で音楽活動も行っている。
夏目 房之介 著
マンガ・コラムニスト、元学習院大学教授。1950年、東京都生まれ。青山学院大学史学科卒。72年、マンガ家デビュー。82~91年、「週刊朝日」にマンガコラム「學問」を連載。96~2009年、「NHK BSマンガ夜話」レギュラー。マンガ、イラスト、エッセイ、講演、テレビ出演など多ジャンルにわたる表現活動で活躍中。夏目漱石の孫。2008~20年度まで学習院大学文学部教授も務めた。著書に『手塚治虫はどこにいる』(ちくま文庫)、『マンガはなぜ面白いのか その表現と文法』(NHK ライブラリー)、『孫が読む漱石』(新潮文庫)などがある。1999年、マンガ批評への貢献により第3回手塚治虫文化賞特別賞受賞。
宇野 常寛 著
1978年生まれ。評論家。批評誌〈PLANETS〉編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、『母性のディストピア』(集英社)。『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』(朝日新聞出版)、『遅いインターネット』(幻冬舎)、石破茂氏との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、対談集『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。立教大学社会学部兼任講師。
商品情報
- 発売日
- 2021年07月26日
- 価格
- 定価:1,210円(本体1,100円)
- 判型
- A5判
- ページ数
- 168ページ
- 雑誌コード
- 6407274
- Cコード
- C9470(芸術総記)
- ISBN
- 978-4-14-407274-1
関連商品

老子×孫子 「水」のように生きる

「幸せ」について考えよう

集中講義 太平記

宗教とは何か

集中講義 夏目漱石

フェミニズム

「わが道」の達人 水木しげる

集中講義 平家物語

パンデミックを超えて

集中講義 ドストエフスキー

集中講義 河合隼雄

萩尾望都

苫野一徳 特別授業『社会契約論』

吉野彰 特別授業『ロウソクの科学』

ナショナリズム

集中講義 三国志

若松英輔 特別授業『自分の感受性くらい』

メディアと私たち

集中講義 宮沢賢治

齋藤孝 特別授業『銀の匙』

わたしたちの手塚治虫

菜根譚×呻吟語

集中講義 大乗仏教

「平和」について考えよう

集中講義 旧約聖書

「日本人」とは何者か?

老子×孫子 「水」のように生きる

「幸せ」について考えよう

集中講義 太平記

宗教とは何か

集中講義 夏目漱石

フェミニズム

「わが道」の達人 水木しげる

集中講義 平家物語

パンデミックを超えて

集中講義 ドストエフスキー

集中講義 河合隼雄

萩尾望都

苫野一徳 特別授業『社会契約論』

吉野彰 特別授業『ロウソクの科学』

ナショナリズム

集中講義 三国志

若松英輔 特別授業『自分の感受性くらい』

メディアと私たち

集中講義 宮沢賢治

齋藤孝 特別授業『銀の匙』

わたしたちの手塚治虫

菜根譚×呻吟語

集中講義 大乗仏教

「平和」について考えよう

集中講義 旧約聖書

「日本人」とは何者か?

老子×孫子 「水」のように生きる

「幸せ」について考えよう
Copyright NHK Publishing, Inc.