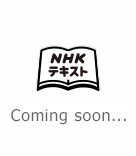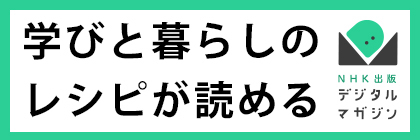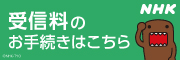カートに追加されました
危機の時代の歌ごころ

品切れ
定価 880円(本体800円)
送料 110円
売り切れました
同じシリーズの商品
この商品を買った人はこんな商品を買っています
商品紹介
災厄と向き合うなかで詠まれた短歌に、人びとの生きる意志を読み解く
戦争、自然災害、公害、社会に潜む差別の問題……時代時代に現れる社会のさまざまな危機に対して、日本人はそれに向き合う心を詩歌に託し、切り抜けようとしてきた。また、現在に至るまで、困難な社会状況を生き抜くための〈武器〉として、詩歌の表現は模索され続けている。
明治時代・与謝野晶子の反戦詩から出発し、太平洋戦争の惨禍、戦後社会の発展に潜む影、震災や新型コロナのパンデミックなど現在進行形の問題まで、社会が直面してきた多様な危機のなかで、いかに詩歌が紡がれてきたのか。とりわけ短歌に着目し、作品そのものの読み解きを軸に、社会のなかで「言葉」を用いてさまざまな理不尽さと闘った歌人たちの軌跡をたどる。
放送情報
放送時間
| チャンネル | 放送日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| ラジオ第2(本) | 日曜 | 午前6:45~7:25 |
| ラジオ第2(再) | 土曜 | 午後6:00~6:40 |
放送年間スケジュール
目次
第一回 「君死にたまふことなかれ」を読む (1) ―反戦詩が攻撃された社会―
第二回 「君死にたまふことなかれ」を読む (2) ―時代に翻弄される詩歌―
第三回 戦争と短歌 1戦地の記録として ―日露戦争・日中戦争―
第四回 戦争と短歌 2祈りのかたち ―沖縄戦・原爆―
第五回 戦争と短歌 3戦中・戦後の女性たち
第六回 災害と短歌 1関東大震災を罹災した歌人たち
第七回 災害と短歌 2短歌の叙事性と震災詠 ―日本海中部地震・阪神淡路大震災―
第八回 災害と短歌 3記録性の自覚・新たな局面 ―東日本大震災―
第九回 社会のなかで社会と闘う 1 高度成長と公害 ―石牟礼道子の心の軌跡―
第十回 社会のなかで社会と闘う 2 差別と偏見 ―社会の病弊として―
第十一回社会のなかで社会と闘う 3 パンデミックの脅威
第十二回社会のなかで社会と闘う 4 行動する短歌 ―原発・沖縄基地問題に抗う―
第十三回社会のなかで社会と闘う 5 現代人の意識に根ざす病
第二回 「君死にたまふことなかれ」を読む (2) ―時代に翻弄される詩歌―
第三回 戦争と短歌 1戦地の記録として ―日露戦争・日中戦争―
第四回 戦争と短歌 2祈りのかたち ―沖縄戦・原爆―
第五回 戦争と短歌 3戦中・戦後の女性たち
第六回 災害と短歌 1関東大震災を罹災した歌人たち
第七回 災害と短歌 2短歌の叙事性と震災詠 ―日本海中部地震・阪神淡路大震災―
第八回 災害と短歌 3記録性の自覚・新たな局面 ―東日本大震災―
第九回 社会のなかで社会と闘う 1 高度成長と公害 ―石牟礼道子の心の軌跡―
第十回 社会のなかで社会と闘う 2 差別と偏見 ―社会の病弊として―
第十一回社会のなかで社会と闘う 3 パンデミックの脅威
第十二回社会のなかで社会と闘う 4 行動する短歌 ―原発・沖縄基地問題に抗う―
第十三回社会のなかで社会と闘う 5 現代人の意識に根ざす病
商品情報
- 発売日
- 2022年06月23日
- 価格
- 定価:880円(本体800円)
- 判型
- A5判
- ページ数
- 192ページ
- 雑誌コード
- 6911060
- Cコード
- C9492(日本文学詩歌)
- ISBN
- 978-4-14-911060-8
- 刊行頻度
- 不定期刊
- NHK
- テキスト