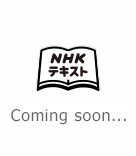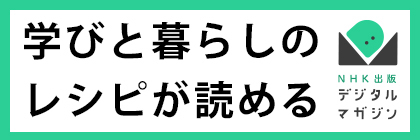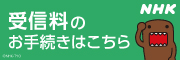カートに追加されました
住まいをよむ

品切れ
定価 880円(本体800円)
送料 110円
売り切れました
同じシリーズの商品
この商品を買った人はこんな商品を買っています
商品紹介
戦後日本における住まいの在り方、人と住まいとの関係性を読み解く。
本テキストでは、主に戦後日本の住まいの在り方に注目し、戦後復興において日本政府が中心に据えた住宅政策や諸制度を概観しながら、住まいにまつわるさまざまな事象(行政・施工法・金融制度・建築業・街づくり等)を、その後のバブル期とその崩壊、人口減少や過疎化に伴う住宅事情の変化までを視野に、時代をおって解説、読み解いていく。
住まいは、建築材料を組み合わせて建設される物理的な空間だが、重要なのは、そこに住むひと・家族の生活が営まれる場所だということ。言い換えれば、住まいとはハードとソフトが渾然一体となった存在なのである。また、住まいには集合住宅やアパートといった形態があり、そこに住む人たちのコミュニティや街づくりにも大きく関係する都市の構成要因でもある。
これらを踏まえ、建築家として第一線で活躍してきた著者が、日本の住まいをめぐる戦後史をたどり、住まいづくりの基本的な考え方、快適な住まい=快適な街づくりのためにできること、すべきことを解説・提言する。
放送情報
放送時間
| チャンネル | 放送日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| ラジオ第2(本) | 日曜 | 午前6:45~7:25 |
| ラジオ第2(再) | 土曜 | 午後6:00~6:40 |
放送年間スケジュール
商品情報
- 発売日
- 2023年12月25日
- 価格
- 定価:880円(本体800円)
- 判型
- A5判
- ページ数
- 192ページ
- 雑誌コード
- 6911076
- Cコード
- C9452(建築)
- ISBN
- 978-4-14-911076-9
- 刊行頻度
- 不定期刊
- NHK
- テキスト