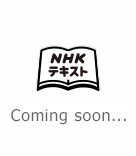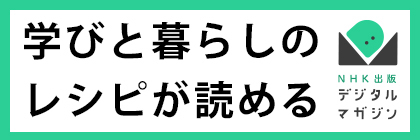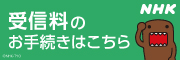カートに追加されました
メディアの歴史から未来をよむ

在庫あり
定価 990円(本体900円)
送料 110円
同じシリーズの商品
この商品を買った人はこんな商品を買っています
商品紹介
メディアの「豊穣な歴史」こそが、複雑化する情報社会を読み解くカギとなる!
ここ数年のあいだにメタバースや生成AIなどの利用が拡大し、デジタルメディアを考察するための理論や思想、調査の方法などはつねに更新が求められている。まったく新しい発想も大切だが、本企画では、古典的な議論が生まれた歴史的背景をふまえつつ、それを現在に活かすすべを考える。電信や電話、写真や映画が発明された19世紀、ラジオやテレビが日常生活と結びついた20世紀を経て、インターネットやスマートフォンが普及した現在に至るまで、メディアと人間、あるいは技術と社会の関係はどう変わってきたのか――。メディア史を通じて、メディア論の基本的な考え方を紹介しつつ、発展を続けるメディアが私たちに何をもたらすのか、社会をどう変えていくのかを考える、13回にわたる番組のテキスト。
本書では紙幅の都合上、通信や放送を中心に扱う。それを軸に、メディア社会の行方を見通すうえで、〈理論〉と〈現実〉、〈過去〉と〈未来〉を切り離して考えるのではなく、双方が分かちがたく結びついているものとしてとらえていく。
併せて、メディアの発展と不可分に関わりながら生まれた、メディア論の古典とされる書物についても紹介。私たちの暮らしと不可分であるメディアの在りようを考える。
放送情報
放送時間
| チャンネル | 放送日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| ラジオ第2(本) | 日曜 | 午前6:45~7:25 |
| ラジオ第2(再) | 土曜 | 午後6:00~6:40 |
放送年間スケジュール
商品情報
- 発売日
- 2024年09月26日
- 価格
- 定価:990円(本体900円)
- 判型
- A5判
- ページ数
- 192ページ
- 雑誌コード
- 6911091
- Cコード
- C9436(社会)
- ISBN
- 978-4-14-911091-2
- 刊行頻度
- 不定期刊
- NHK
- テキスト