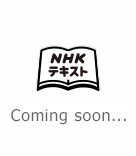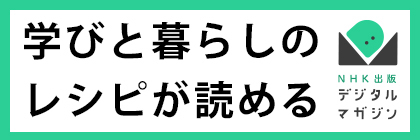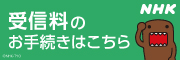カートに追加されました
茶の湯 藪内家 薄茶の味わい

在庫あり
定価 1,100円(本体1,000円)
送料 110円
同じシリーズの商品
商品紹介
薄茶点前に込められた工夫や趣向を味わい、茶の湯のもてなしの心を学ぶ
藪内家は14代400年の歴史を持ち、千利休の侘茶と古田織部の武家茶、両方の特徴を併せ持つ。今回は、藪内家の由緒ある茶室、道具を用い、薄茶点前の基本を学ぶ。茶の湯の楽しみは、客としてもてなされる側、亭主としてもてなす側の双方にある。亭主は、茶会当日まで趣向や道具組を考え、茶会では亭主、客がともに会話による一期一会の出会いを味わう。
導入では藪内家の茶室「燕庵」のにじり口や点前座を紹介、藪内家の歴史に触れる。第1回では、客としてスムーズにお茶をいただけるよう、茶席の持ち物、装い、所作などから、点前座の道具、実際の作法の基本を紹介。第2回では、茶巾をたたむ、ふくささばき、茶筅とおしなど「割稽古」で基本の点前動作を身につける。第3回では、点前の準備からお茶を点てる、茶器と茶杓の拝見など、亭主と客の所作を通じて一連の薄茶点前を行う。第4回は亭主の立場から、軸や茶器を選び、菓子や見立ての用意など、工夫や趣向の凝らし方を紹介。席入りの挨拶から薄茶点前で客をもてなす実際を学ぶ。点前を通して身につけることで、巧拙の差はあれ、亭主としてだれでも茶の湯で客をもてなす魅力を味わえる。
読み物「茶の湯 学ぶ楽しむ」では、宗匠がお茶を献ずる「皇女和宮御尊前献茶式」。藪内家の流祖・剣仲をしのぶ燕庵での「流祖剣仲忌」茶会。「炉の季節、風炉の季節」を味わう12代猗々斎にちなんだ朝稽古。藪内家が力を入れる茶の湯を学ぶ若者の育成の実際として、龍谷大学茶道部での稽古も紹介する。
放送情報
放送時間
| チャンネル | 放送日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| Eテレ(本) | 火 | 午後9:30~9:55 |
| Eテレ(再) | 翌週火 | 午後0:15~0:40 |
放送年間スケジュール
目次
第二回 点前の基本
第三回 薄茶点前
第四回 薄茶の茶会
商品情報
- 発売日
- 2024年02月26日
- 価格
- 定価:1,100円(本体1,000円)
- 判型
- AB判
- ページ数
- 96ページ
- 雑誌コード
- 6228867
- Cコード
- C9476(諸芸娯楽)
- ISBN
- 978-4-14-228867-0
- 刊行頻度
- 不定期刊
- NHK
- テキスト